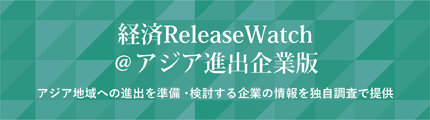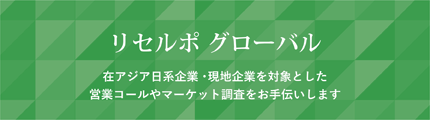海外営業・マーケティングコラム
2025-05-29
企業の実感が語るアジア各国の姿 ― 営業利益・FDIから読む進出地の“温度差”
近年、アジア諸国に進出している企業の景況感には、国や地域によって大きな差が見られます。とくに営業利益の見通しは、現地市場の実感を最も端的に映し出す指標のひとつとして注目されています。
各国の企業活動を取り巻く環境が複雑さを増すなか、どの国の需要が伸びているのか、どこに商機を見出す企業が増えているのかを見極めるには、こうした足元の数字にこそ手がかりがあります。
本記事では、営業利益の見通しを手がかりに、アジア各地の現地市場に対する企業の期待や不安の内実を読み解いていきます。
営業利益が語る「伸びている国」
アジア地域における市場の手応えを測るうえで、有力な指標となるのが、現地拠点を持つ企業による営業利益の見通しです。これは為替や調達コストといった要因も含まれますが、それらを踏まえたうえでも黒字を見込む企業が多い国では、需要の堅調さや事業環境への前向きな見方があると考えられます。
日本貿易振興機構(ジェトロ)が実施した「2024年度 海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)」によれば、調査対象となった各国・地域の現地拠点(現地法人、支店、駐在員事務所など)において、営業利益を「黒字」と見込むと回答した割合は、全体平均で65.8%に上りました。
なかでも注目されるのがインドです。黒字見込みと回答した拠点の割合は77.7%に達し、2008年以降で最も高い水準となっています。回答理由からは、現地需要の増加が利益見通しを押し上げている様子が読み取れます。こうした動きは、販売面・投資面の両方における積極姿勢とも連動していると見られます。
一方で、黒字割合そのものでは、台湾(81.3%)や韓国(80.4%)もインドを上回る水準を示しています。これらの地域では、販売型ビジネスが中心であることや、景気回復の波を早期に取り込めたことなどが、収益性を支える背景にあると考えられます。ただ、いずれも過去にも高水準の黒字見通しが示されていた地域であり、今後の上昇余地という点では、インドのように継続的な伸びが意識されている国とは少し異なる位置づけです。
東南アジア各国もまた、堅調な動きを見せています。インドネシアでは72.1%、マレーシアでは70.8%、フィリピンでは69.8%、シンガポールでは65.9%、ベトナムとタイはいずれも64.1%が黒字と見込んでおり、全体平均と同等かそれ以上の水準です。現地市場の需要や拠点の安定性が、収益面での見通しを下支えしているとみられます。
一方で、中国における現地拠点では営業利益を黒字と見込む割合が58.4%にとどまり、2013年以降で最低となりました。現地需要の低下や競争環境の厳しさが、収益見通しに影を落としていると推測されます。実際に、調査では「需要減少」や「競争激化」が主な悪化要因として挙げられており、一部では事業方針の見直しや地域分散の動きも見られます。
このように、各国の現地拠点から寄せられた営業利益の見通しには、企業がその市場にどれだけの商機を見いだしているかが率直に表れています。単なる業績指標ではなく、現地市場の温度感を知るうえでの、重要な手がかりとなります。
「現地需要」の実感が企業の意志を決める
営業利益の見通しが明るい国では、企業のあいだで「現地市場の需要が回復している」「商機を感じる」といった感覚が共有されつつあります。ジェトロの調査では、こうした利益見通しの改善を支える要因として、最も多く挙げられているのが「現地市場での需要増加」です。これは、全体の47.4%の企業が選択しており、他の選択肢と比べても突出しています
。
この傾向は特定の国において特に顕著です。インドでは、営業利益の改善理由として「現地需要の増加」を挙げた企業が76.7%に上っており、韓国や台湾でも6割を超えています。これは単に景況感が良いという以上に、「売れる見込みがある」という手応えに基づいて、現地拠点での取り組みを積極化させている姿勢を反映しています。
企業が現地での活動を拡大するかどうかの判断には、制度やコスト、パートナーの有無などさまざまな要素が影響しますが、最終的にそれを後押しするのは「売れそうかどうか」という実感です。今回の調査結果は、それを裏付ける形となっています。
一方、営業利益の悪化要因についても、最多の回答は「現地市場での需要減少」でした。中国、タイ、ミャンマー、インドネシアなどでは、この理由を挙げた企業が過半数に達しています。価格競争の激化やコスト上昇といった構造的な問題も存在しますが、需要の勢いそのものが鈍っているという感覚は、企業の行動にとって非常に重い意味を持ちます。
調達やサプライチェーンの構築には時間がかかる一方、販売先の需要動向にはある程度の即応が求められます。そのため、「需要があるかどうか」という問いに対する現地の実感が、拠点強化や撤退、新規進出の判断に直接つながりやすいのです。
数字に表れる黒字割合や利益改善の要因は、そうした企業の主観的な手応えを集積した結果でもあります。需要に対する実感は、いわば最前線の現地拠点が肌で感じている変化であり、それが意志決定の基礎になっていることは明らかです。
インドの存在感と東南アジアの持続性
2024年調査で営業利益見通しが最も高かったのは台湾でしたが、過去からの高水準を維持している点を踏まえると、今後の伸びしろという観点では、インドの存在感が際立ちます。黒字見込みが77.7%と、調査開始以来の最高値を記録していることからもわかるように、企業にとってインドは「これからさらに伸ばしていける市場」として捉えられていることがうかがえます。
利益の見通しが良好な国では、今後の拠点強化や投資拡大への意志も高まりやすくなります。インドについては、営業面だけでなく製造・開発分野でも進出の動きが活発化しており、単なる消費市場としての位置づけを超えて、複数の役割を担う戦略拠点と見なす企業が増えているようです。この傾向は、今後の事業ポートフォリオの見直しにも直結していく可能性があります。
一方で、東南アジアに対する企業の見方は、急成長というよりも「安定した収益が見込める市場」としての評価が目立ちます。インドネシアやマレーシア、フィリピンなどでは営業利益の黒字見通しが高く、現地での収益性が一定水準で維持されていることが確認できます。企業側も、これらの国々に対しては「手堅く利益を積み重ねられる場所」として着実に対応している様子が見て取れます。
また、東南アジアには複数国にまたがって生産や販売のネットワークを構築している企業も多く、特定国への依存リスクを分散しやすいという利点があります。このことは、単一市場への依存がリスクとなりやすい現代の国際事業戦略において、重要なポイントの一つです。ベトナムやタイなどで営業利益の見通しが前年より下がっているケースもありますが、それでも一定の水準を保っており、急速な悪化とまでは言えません。
今後、インドが規模と成長性の両面で注目される存在であり続ける一方で、東南アジアは地道な収益基盤としての価値を持ち続けると見られます。企業が両者をどう位置づけ、どのような配分でリソースを投じていくかが、アジア戦略全体の方向性を左右することになりそうです。
FDIの視点から見る国際的な視線の移動
営業利益見通しが企業の内部的な意志を示す指標であるとすれば、外国直接投資(FDI)は外部からその国・地域に対する関心や信頼がどれほど向けられているかを示すデータです。FDIの動向を見ることで、現地の市場や産業に対する国際的な評価や期待がどこに集まりつつあるのかを読み取ることができます。
国連貿易開発会議(UNCTAD)が発表した最新の「世界投資報告書」によれば、2023年におけるアジア全体のFDI流入額はおおむね横ばいでしたが、国別で見るとその内訳には明確な差が現れています。中国のFDI流入額は減少傾向を示しており、外資企業が現地事業の拡大に慎重になっている様子がうかがえます。中国の市場規模やインフラ整備の水準はいまだ魅力的ではあるものの、政策や制度の不透明感が外資にとっての参入ハードルとなっているという指摘も見られます。
その一方で、インドは着実にFDIを集めており、IT・製造分野を中心に外資企業の進出が続いています。制度整備やデジタル化推進に加え、人口構成の若さや内需の拡大余地が長期的な魅力と映っているようです。また、グローバル企業の中には、従来中国に集約していた製造・調達機能の一部をインドに移す動きも見られ、これが投資先としての存在感を高める要因の一つとなっています。
東南アジアも、FDI受け入れ先として引き続き注目を集めています。特に、ベトナムやインドネシア、マレーシアなどでは、労働力の確保やコスト面での優位性に加え、国際的な経済連携協定の進展が外資の参入を後押ししています。また、複数の国にまたがってサプライチェーンを構築する動きが進む中で、東南アジア全体が「ポートフォリオとしての拠点群」として捉えられつつある点も特徴です。
このように、FDIという外部からの視線を通じて見ると、各国の魅力や課題がより立体的に浮かび上がってきます。どの国に資本が集まり、どのような機能が期待されているのかを捉えることで、進出先ごとの立ち位置や役割をより具体的に考えることができます。
各国の違いから考える拠点戦略
営業利益の見通しと外国直接投資(FDI)の動きは、それぞれ異なる観点から各国の魅力を浮かび上がらせる指標です。利益見通しは現地で事業を営む企業の体感を、FDIは外部から見た成長可能性への評価を反映しています。この二つを対比させて見ることで、単純な「良し悪し」ではなく、国ごとの立ち位置や企業が置かれている状況の違いが見えてきます。
たとえばインドは、営業利益の黒字見通しが過去最高を記録する一方で、FDIの流入も堅調です。収益性と成長性の両方が評価されている国として、企業が複数の役割を与えたくなるような市場だといえます。製造・販売・開発といった異なる機能を同時に担わせることができる拠点として、存在感を強めています。
東南アジアでは、マレーシアやインドネシア、フィリピンといった国々が利益面での安定感を見せています。FDIの受け入れも継続しており、既存拠点の機能強化や分散拠点としての価値が認識されていることがうかがえます。一方で、ベトナムのように、営業利益の見通しがやや落ち着く中でも、投資の勢いが持続している国もあります。これらの国では、立ち上げや拡張に伴うコストが一時的に収益を圧迫している可能性もあり、投資先行型の展開が多いことを示唆しています。
台湾や韓国は、営業利益の黒字見通しが極めて高く、事業の採算性が確立している地域といえます。一方で、既に進出が進んでいることから新規のFDIは落ち着きつつあり、「安定収益を得る場所」としての性格が強まっている印象があります。こうした国では、効率化や収益最大化のフェーズに入っている企業が多いと考えられます。
一方、中国では営業利益の黒字見通しが2013年以降で最低となり、FDIも減少傾向にあります。企業の間では、従来の前提を見直す動きも出てきており、単なる撤退か存続かといった二択ではなく、「この地域にどういう役割を持たせるべきか」という再設定が進んでいるようです。
このように、利益と投資という二つの軸を通じて各国の状況を見比べると、地域ごとの温度感や進出フェーズの違いが鮮明になります。
まとめ
各国に拠点を持つ企業の視点から見た営業利益の見通しと、外部資本が向かう先としてのFDIの動き。その両面からアジア諸国を見渡すことで、単純な市場規模や地域ラベルだけでは語れない、それぞれの国の現在地と企業の期待感が浮かび上がってきました。
インドは収益性と投資誘因の両面で存在感を高め、より複合的な役割を与えられる市場としての性格を強めつつあります。一方、東南アジアの各国は、収益の安定感や機能分散の受け皿としての価値が継続的に認識されており、個別に見れば立ち上げ段階にある国と成熟段階に入っている国が混在しています。
台湾や韓国のように採算性が確立している地域では、事業の効率化や最適化が進み、中国のように変化の渦中にある国では、役割再設定を含む柔軟な見直しが求められています。いずれにしても、企業が各国に対して抱く「何を期待し、何を委ねるか」という意図が、数値の裏側に色濃くにじんでいるように見受けられます。
市場ごとのステージやポジションを見極め、その違いに応じた戦略的な構えを持つこと。今後のアジア展開において、拠点の分布や機能を見直すうえでの基礎材料は、すでに企業の実感や投資行動の中に現れ始めています。
もどる