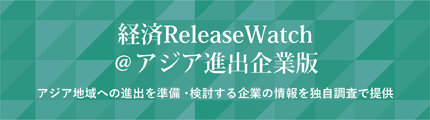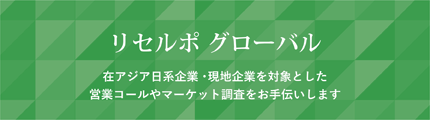海外営業・マーケティングコラム
2025-06-20
加速する日本企業のベトナム展開 ― ここ5年の進出トレンドを読む
日本企業のベトナム展開は、過去5年間にわたって安定したペースで拡大を続けてきました。コロナ禍でも進出件数は大きく落ち込むことなく、近年では製造業に限らず、IT、サービス、小売など多様な業種が現地市場に入り始めています。背景には、チャイナ・プラス・ワン戦略やASEAN域内連携の深化だけでなく、現地人材や中間層市場への注目もあります。本稿では、日本企業のベトナム展開を「勢い」と「展開の中身」の両面から読み解き、その変化と広がりを考察します。
高水準で続く日本企業のベトナム進出
日本企業のベトナム展開は、過去5年間にわたり安定した拡大を続けています。外務省「海外進出日系企業拠点数調査」によると、ベトナムにおける日系企業の拠点数は2019年10月時点で1,944件、2023年10月には2,394件へと増加。約23%の拡大は、コロナ禍をはさみながらも現地展開の勢いが鈍っていないことを示しています。
パンデミック期には各国で一時的な縮小や撤退の動きも見られましたが、ベトナムにおいては進出のペースが極端に落ち込むことはなく、すでに拠点を構えていた企業による再投資や機能拡張といった動きも並行して進みました。製造業を中心とする進出が主流である点は今も変わりませんが、後述するように非製造業を含む多様な業種の参入も目立ち始めています。
収益面では、近年の調査においてベトナム進出企業の黒字比率はASEAN全体の平均に近い水準で推移しており、特に優れているわけではないものの、事業全般に深刻な問題があると見なされる状況でもありません。むしろ、平均的な業績にもかかわらず投資の勢いが持続している点は、ベトナム市場に対する中長期的な信頼感のあらわれといえるでしょう。
近年では、「新たに出る」だけでなく、「既存拠点の再配置」や「複数都市での多拠点展開」といった戦略的な広がりも見られます。これは、ベトナムにおける事業展開が一過性ではなく、企業の中核に組み込まれつつあることを示す動きでもあります。
「中国リスク」だけではないベトナムの選ばれ方
日本企業のベトナム進出について語る際、「チャイナ・プラス・ワン」というキーワードが頻繁に登場します。これは、中国に生産拠点や調達網を集中させるリスクを避けるため、代替または補完的な拠点として他国を併用する戦略です。実際、2010年代以降、米中摩擦や中国国内の人件費高騰を受けて、東南アジア諸国のなかでもベトナムはその有力候補として位置づけられてきました。
しかし、ここ数年のベトナムの動向を見ると、その選ばれ方はもはや「中国の代替地」という枠にとどまっていません。企業がベトナムに拠点を構える理由は、地政学的な比較優位や制度環境、現地市場の可能性といった複数の要素が絡み合っています。
まず地理的に見ても、ベトナムは南シナ海に面し、中国やASEAN主要国と接続しやすい位置にあります。北部は中国と陸路でつながり、中部・南部からはASEAN各国やインド洋地域へのアクセスも容易です。これは、原材料や部品の調達、完成品の輸出をグローバルに展開する企業にとって、大きな利点となります。
制度面でも、ベトナムは自由貿易協定(FTA)の締結を積極的に進めてきました。TPP11(CPTPP)やEU・ベトナム自由貿易協定(EVFTA)、RCEPなど、アジアと欧州の両方をカバーする枠組みに加盟しており、関税の優遇やルールの明確化といったメリットが投資判断に影響を与えています。とくに製造業においては、輸出入コストを抑えつつ、サプライチェーンを効率的に運用できる環境が整いつつあります。
加えて、政治的安定性と親日的な国民感情も見逃せない要素です。長期にわたる経済成長と、国策としての外資受け入れ方針が一貫しており、政情や制度変更のリスクが比較的低いことは、現地展開を検討する企業にとって安心材料となります。また、人的資源としての労働力も豊富で、教育水準の底上げやエンジニア人材の育成支援など、量と質の両面での成長が期待されています。
これらを踏まえると、ベトナムが「中国依存のリスクヘッジ先」としてだけでなく、「自らの魅力と戦略性で選ばれる国」になりつつあることがわかります。東南アジアのなかでも、とくに地に足のついた成長が期待できる国として、ベトナムは独自の立ち位置を築いているのです。
広がる業種と機能 ― “拠点”の意味が変わってきた
かつて、日本企業にとってのベトナム進出は、低コストでの生産を目的とした製造拠点の設置が中心でした。しかし近年、その構図に変化が見られます。業種の広がりに加え、拠点に求められる役割そのものが多様化しており、「つくる場所」という従来の意味を超えた展開が進んでいます。
たとえば、ITやデジタル関連分野では、オフショア開発の受託先としてだけでなく、自社の開発・設計機能を持つ現地法人の設立が増加しています。若年層の多さや技術教育の底上げにより、エンジニア人材の採用競争力が高まり、ベトナム国内でプロジェクトマネジメントや上流工程に対応できる体制を構築する企業も出てきました。単なる“外注先”ではなく、グローバル開発体制の一角として位置づける例もあります。
小売やサービス業においても、現地の中間層の成長を背景に出店が進んでいます。ユニクロや無印良品、イオンなどの日本ブランドが都市部を中心に出店を重ねており、現地ニーズに合わせた品揃えや価格設計を通じて、ベトナム市場向けのビジネスモデルを模索しています。これに伴い、マーケティング・商品企画・物流最適化などの機能が現地法人内に取り込まれるケースも増えてきました。
また、B2B領域でも変化が起きています。会計・法務・人材紹介といったプロフェッショナルサービスが、製造業の進出に伴ってベトナム市場に展開されつつあり、特定業種の付帯機能にとどまらない独立した事業領域としての定着が進んでいます。さらには、スタートアップ企業や大学との連携を通じて、研究開発や実証事業を現地で行う動きも一部に見られ、ベトナムの拠点が単なる出先機関ではなく、事業創出の現場となるケースも出てきました。
こうした変化は、ベトナムが「安くつくる場所」から「事業の前線基地」へと認識を変えていることの表れでもあります。拠点の意味が“生産”から“展開”へと広がる中で、企業はベトナムに対してより長期的な視点で関与しようとしています。進出件数の増加だけでは見えてこない、質的な広がりが今まさに進行中だと言えるでしょう。
進出企業が向き合う変化と課題
ベトナムにおける日本企業の展開は拡大を続けていますが、環境が変化すれば、それに伴って向き合う課題も変わっていきます。とくに近年では、現地の人材、市場、制度、文化に対する向き合い方において、従来と同じやり方では通用しない場面が増えつつあります。
まず、多くの企業が直面しているのが「現地人材の活用」に関する課題です。かつては、日本側で設計・意思決定を行い、ベトナムでは製造や運用といった定型的な業務を担うという分業が一般的でした。しかし、業務の高度化とともに、現地スタッフにもより高い判断力や専門性、マネジメント力が求められるようになっています。ところが、日本と同じ基準で人材を採用・育成しようとすると、うまくいかないケースも少なくありません。キャリア観や転職意欲の高さ、昇進スピードへの期待など、現地特有の価値観を理解し、現実的な運用を組み立てることが必要です。
また、企業のガバナンスにおいても、変化への対応が求められています。ベトナムの制度環境は年々整備が進んでいますが、その一方で法制度の改正頻度が高く、手続きの煩雑さや実務レベルでの解釈の違いがトラブルの原因となることもあります。現地法人に一定の裁量を与える一方で、日本本社としての統制と連携をどう維持するかは、多くの企業にとって悩ましい課題です。とくに拠点の機能が広がりを見せる今、本社側の理解と柔軟性も求められる場面が増えています。
市場との向き合い方もまた、見直しが迫られている分野です。ベトナム国内で事業展開する際、単に日本と同じ製品やサービスを持ち込むだけでは支持を得られない場面が増えています。中間層を中心とした消費者の感性や価格感覚は、日本とは大きく異なり、現地目線での調査や企画、カスタマイズが不可欠です。また、競合も日系企業だけでなく、韓国や中国、地場の企業が多く存在する中で、単なる「品質の良さ」だけでは差別化が難しい領域も増えています。
これらの課題を乗り越えるには、ベトナムを単なる生産拠点やコスト拠点としてではなく、事業を一緒に築く“現地パートナー”と位置づける発想が求められます。人材、制度、市場、文化といった多層的な環境に対応しながら、拠点を育て、現地とともに成長していく。その視点なしに、進出の「広がり」は維持できないフェーズに入っているのかもしれません。
まとめ ― 「加速」と「変化」の両面をとらえる
この5年間を振り返ると、日本企業によるベトナム展開は件数・規模ともに着実に拡大を続けており、「加速」という表現が決して大げさではないことが確認できます。とりわけ注目すべきは、この拡大が一過性ではなく、パンデミックや国際情勢の変動を含む不安定な時期を経ても持続している点です。高い進出意欲が維持されているという事実は、ベトナム市場の安定性と将来性への信頼のあらわれでもあります。
同時に、拠点の“かたち”にも変化が起きています。製造業を中心とした展開から、ITや小売、B2Bサービスなど非製造領域へも広がりが見られ、現地における拠点の機能も多様化してきました。設計や研究、マーケティング、現地市場向け商品企画など、従来は日本本社に置かれていた業務が一部ベトナム側に移されるなど、役割の再定義が進んでいます。進出=生産、という等式はもはや成り立たなくなりつつあるのです。
もちろん、この変化は必ずしも平坦なものではありません。人材の採用・育成、制度面の運用、現地市場への対応といった多様なテーマにおいて、日本企業側にも再適応が求められています。とくに、現地法人が自立して機能するには、本社側の理解や柔軟性、そして「現地を信じて任せる姿勢」が欠かせません。ベトナムでの展開が量的に進むほど、その中身の構築と維持がより重要になるという側面もあります。
今後を展望すると、ベトナム市場は引き続き注目すべき対象であることに変わりはありません。ただし、その関わり方はより長期的かつ戦略的なものへと進化していくことが求められます。単なる進出や生産拠点の設置ではなく、どのように拠点を育て、現地とどう関係を築いていくか。その問いに対する答えが、ベトナム展開の成否を左右していくでしょう。
「加速」が数字としての広がりを示すなら、「変化」はその中身の深まりを意味します。両者を同時に捉える視点が、これからのベトナム戦略には欠かせません。
もどる