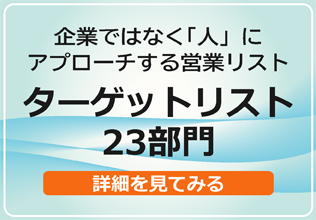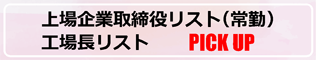2025-12-18
「分かっていた」はどこから生まれるのか― 後知恵バイアスと振り返りの構造
BtoB 営業・マーケティング コラム
結果を知った後で、過去の判断を振り返ってみると、「振り返れば、こうなる可能性も考えていた気がする」と感じることがあります。強くそう思い込んでいたわけではないものの、説明を与えられると違和感なく受け取れてしまう。こうした感覚は、誰にでも起こり得るものです。
認知心理学では、このように結果を知った後で過去の不確実性を小さく見積もってしまう傾向を「後知恵バイアス」と呼びます。重要なのは、これは感情的な判断ミスや経験不足の問題ではなく、理性的に考えようとする人ほど陥りやすい認知の特性だという点です。
本記事では、後知恵バイアスがどのように生まれ、判断や評価、そして学習のあり方にどのような影響を及ぼすのかを整理します。結果論に引きずられず、次の判断をより確かなものにするための前提として、この認知の癖を見つめ直していきます。
目次
「分かっていたはずだ」という感覚はどこから生まれるのか
結果を知った後に過去の判断を振り返ると、その判断が当時よりも単純に見えてくることがあります。複数の選択肢が存在していたはずにもかかわらず、「振り返れば、この結果に落ち着く流れだった」と感じてしまう。このとき私たちは、判断時点で存在していた不確実性を、意識しないまま縮小して捉え直しています。
認知心理学では、このような傾向を「後知恵バイアス」と呼びます。結果を知った後、人は過去の状況を現在の知識を前提に再構成し、「そうなる可能性は見えていた」「ある程度は予測できていた」という感覚を持ちやすくなります。心理学者 Kahneman は著書※1 の中で、人間の判断は常に直感的な思考と熟慮的な思考の影響を受けており、結果が与えられた状況では直感的な理解が優位になりやすいと述べています。後知恵バイアスは、まさにこの直感的な理解が過去の判断を上書きする場面で強く表れます。
ここで注意すべきなのは、「分かっていたはずだ」という感覚が、当時実際にそう考えていたことを正確に反映しているとは限らない点です。判断の時点では、情報は限定的であり、複数の展開が並存していました。しかし結果が確定すると、それ以外の可能性は背景に退き、実際に起きた出来事だけが一貫した物語として浮かび上がります。
社会心理学者の Fischhoff は研究※2 において、結果を知ることが人の判断評価にどのような影響を与えるかを検証しました。この研究では、被験者に対して歴史的事件や社会的な出来事について、複数の結果が起こり得る状況を提示し、それぞれの結果が起こる確率を見積もらせました。その後、実際に起きた結果を知らされた上で、改めて「当時、自分はどの程度その結果を予測していたと思うか」を回答させています。
その結果、被験者は、結果を知る前に自分が見積もっていた確率よりも、「その結果は起こりそうだと考えていた」と後から評価する傾向を示しました。つまり、結果を知った時点で、過去の判断に関する記憶そのものが修正され、「分かっていた」という感覚が強化されていたことが示唆されています。
この再構成は、意図的な自己正当化によって起こるとは限りません。むしろ多くの場合、本人にとっては自然で違和感のない理解として成立します。そのため、理性的に振り返っているつもりであっても、評価の前提となる過去の状況理解がすでに変化していることに気付きにくい。この点に、後知恵バイアスの捉えにくさがあります。
【出典】
※1 Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.
※2 Fischhoff, B. (1975). Hindsight ≠ Foresight: The Effect of Outcome Knowledge on Judgment under Uncertainty. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance.

後知恵バイアスは「判断」よりも「評価」を歪める
後知恵バイアスは、判断を下している瞬間よりも、その判断を振り返り、評価する場面で強く作用します。判断時点では、情報は限られており、複数の可能性が並存しています。しかし結果が明らかになった途端、その不確実性は意識の外に退き、判断は「結果に至るまでの合理的な過程」として理解されやすくなります。
このとき変化しているのは、判断の内容そのものではありません。変わるのは、その判断をどう評価するかという視点です。結果が良ければ判断も妥当だったと感じやすく、結果が悪ければ判断そのものに問題があったと結論付けやすい。結果が評価の中心に入り込むことで、判断時点に存在していた制約や不確実性が、十分に考慮されなくなります。
この評価の歪みは、心理学者の Baron と Hershey による研究※3 でも確認されています。彼らの研究では、成功率が80%と説明された手術を実施するかどうかを判断した医師の意思決定を、第三者が評価するという課題が用いられました。判断時点では、成功と失敗の可能性はいずれも存在しており、統計的に見ればその判断は合理的なものです。
ところが、実際に手術が成功したと知らされた場合、その判断は高く評価されやすくなり、反対に失敗に終わったと知らされた場合には、「別の選択肢を取るべきだった」と評価されやすくなりました。判断に用いられた情報や条件が同じであっても、結果を知ることで評価が大きく変わってしまう。この研究は、結果が評価の基準そのものを押し動かすことを示しています。
後知恵バイアスは、まさにこの評価の場面で作用します。結果を知った状態では、判断時点での不確実性を正確に思い出すことが難しくなり、「分かっていたはずだ」「避けられたはずだ」という感覚が生まれやすくなります。その結果、判断の良し悪しが、結果の良し悪しと結び付けられて理解されてしまいます。
このような評価の仕方は、学習にも影響を及ぼします。結果が良かった判断は検証されないまま正解として記憶され、結果が悪かった判断は単純な失敗例として整理されがちです。しかし、本来検討すべきなのは、判断時点で何が分かっていて、何が分かっていなかったのかという条件の整理です。評価が結果に引きずられるほど、次の判断に活かせる情報は失われていきます。
【出典】
※3 Baron, J., & Hershey, J. C. (1988). Outcome Bias in Decision Evaluation. Journal of Personality and Social Psychology, 54(4)
「学んだつもり」が次の判断を弱くする理由
後知恵バイアスの影響は、単に過去の判断をどう評価するかにとどまりません。結果を振り返り、「理解できた」「学んだ」と感じる過程そのものにも作用します。その結果、振り返りを行っているつもりでも、次の判断に十分に活かせない状態が生まれます。
結果が良かった判断は、「妥当だった」「正しかった」と整理されやすくなります。その際、どの前提が偶然うまく当たったのか、どの点に不確実性が残っていたのかといった検討は後回しにされがちです。一方、結果が悪かった判断は、「判断を誤った」と単純に結論付けられやすく、判断時点の情報条件や制約を丁寧に振り返る機会が失われます。こうして、結果を軸にした理解が積み重なることで、「学んだつもり」の整理が成立していきます。
後知恵バイアスについて整理した心理学者の Roese と Vohs の研究※4 では、この過程が段階的に進むことが示されています。結果を知った後、まず当時の判断や予測に関する記憶が、結果に沿う形で書き換えられます。次に、その結果が「そうなる流れだった」と感じられるようになり、出来事の必然性が強調されます。最後に、「分かっていた」「ある程度は予測できていた」という感覚が生まれ、振り返りは納得感のある説明としてまとまります。こうして整えられた理解は一見もっともらしく見えますが、判断時点に存在していた不確実性は、その過程で見えにくくなっています。
この研究の中では、こうした振り返りが、理解を深めたという感覚を生みやすい一方で、判断の前提条件を正確に捉え直すことにはつながりにくい点も指摘されています。結果を前提に組み立てられた説明は、納得しやすく記憶にも残りやすいものの、次に同様の状況に直面した際の判断材料としては十分でない場合があります。
この「学んだつもり」は、自信の持ち方にも影響します。結果を説明できるほど、自分の判断力が向上したように感じられますが、その自信が判断時点の不確実性を過小評価する方向に働くこともあります。過去の結果に基づいて形成された理解が、次の判断における前提として固定されてしまうと、新たな情報や別の可能性に目が向きにくくなります。
本来、振り返りで確認すべきなのは、結果そのものではなく、判断時点の条件です。何が分かっていて、何が分かっていなかったのか。どの仮定を置き、どこに幅を持たせていたのか。後知恵バイアスの影響を受けた振り返りでは、こうした要素が結果の背後に隠れてしまいます。その結果、「理解した」という感覚だけが残り、次の判断を支える材料が十分に蓄積されないままになります。
【出典】
※4 Roese, N. J., & Vohs, K. D. (2012). Hindsight Bias. Perspectives on Psychological Science, 7(5)
後知恵バイアス研究の整理と位置付け
後知恵バイアスは、複数の研究を通じて少しずつ理解が積み重ねられてきました。『「分かっていたはずだ」という感覚はどこから生まれるのか』で触れた社会心理学者の Fischhoff の研究で示されたのは、結果を知った後、人は当時の見立てを実際よりも高く見積もり直してしまうという現象です。結果が分かった瞬間、過去の不確実性が縮み、「そうなる流れだった」と感じやすくなる。この点が、後知恵バイアスの基本的な出発点として位置付けられています。
その後、『後知恵バイアスは「判断」よりも「評価」を歪める』で扱った心理学者の Baron と Hershey の研究では、問題が予測の歪みにとどまらず、判断の評価にも関わることが示されました。判断条件が同じであっても、結果の良し悪しによって評価が変わってしまう。この研究は、後知恵バイアスが「振り返り」や「評価」という場面でどのように現れるかを整理する上で、重要な位置を占めています。
さらに、『「学んだつもり」が次の判断を弱くする理由』で取り上げた心理学者の Roese と Vohs の整理では、後知恵バイアスが単一の反応ではなく、いくつかの認知的な過程が重なって生じる現象として説明されています。結果を知った後に記憶が再構成され、出来事が必然だったように理解され、最後に「分かっていた」という感覚が形づくられる。この整理によって、後知恵バイアスは個別の判断ミスではなく、振り返りの過程そのものに組み込まれた認知の特性として位置付けられるようになりました。
実在研究・企業事例に見る後知恵バイアスの影響
後知恵バイアスは、判断そのものよりも、「結果を知った後の評価」や「振り返り」の場面で強く表れます。この特徴は、実験室の中だけでなく、実務に近い状況を扱った研究でも確認されています。ここでは、専門家や企業の意思決定を対象にした実在研究を通して、後知恵バイアスがどのように現れるのかを見ていきます。
まず、結果を知った状態で評価せざるを得ない領域として、司法判断があります。心理学者の Oeberst と Goeckenjan は論文※5 の中で、過失判断における後知恵バイアスを検証しています。この研究では、実際の判例に基づいた医療過誤の事案を用い、日常的に過失判断を行っている裁判官に対して、ある医療行為についての経緯を提示しました。その際、一部の裁判官には最終的な結果を知らせた上で判断を求め、別の裁判官には結果を伏せたまま同じ評価を求めています。
その結果、結果を知らされた裁判官の方が、「当時でもその結果は予測できたはずだ」と判断しやすくなり、過失を認める評価が厳しくなる傾向が見られました。結果を先に知ってしまうことで、判断時点では不確実だった状況が、後から見ると分かりやすく見えてしまう。この研究は、専門的な判断を行う立場にある人であっても、結果を知った評価から完全に自由ではいられないことを示しています。
同様の構造は、企業の戦略判断を対象にした研究でも確認されています。経営学者の Bukszar は論文※6 の中で、戦略的な意思決定を行った後の評価に、後知恵バイアスがどのように影響するかを検証しました。この研究では、企業の意思決定を想定した複数の戦略シナリオを提示し、それぞれについて、結果を知った状態と知らない状態で、判断の妥当性を評価させています。
その結果、同じ判断であっても、成功したと知らされた場合には「合理的で適切な判断だった」と評価されやすく、失敗したと知らされた場合には「判断に問題があった」と評価されやすい傾向が確認されました。重要なのは、評価が変わったのは判断の内容そのものではなく、結果を知っているかどうかだけだった点です。判断時点では複数の選択肢があり、不確実性の中で意思決定が行われていたにもかかわらず、結果を知った後では、その不確実性が評価の中から抜け落ちてしまいます。
これらの研究が示しているのは、後知恵バイアスが「判断を誤った人の問題」として生じるのではなく、「結果を前提に評価し、説明しようとする構造」の中で自然に生まれるという点です。司法の場でも、企業の意思決定でも、結果が共有された後に評価が行われる限り、当時の状況は単純化されやすくなります。
実在研究を通して見ると、後知恵バイアスは特定の職業や分野に限られた現象ではありません。結果が明らかになり、その説明や評価が求められる場面であれば、誰にとっても起こり得る。その前提を共有することが、判断や評価を冷静に捉え直すための出発点になります。
【出典】
※5 Oeberst, A., & Goeckenjan, I. (2016). When being wise after the event results in injustice: Evidence for hindsight bias in judges' negligence assessments. Psychology, Public Policy, and Law, 22(3)
※6 Bukszar, E. (1988). Hindsight bias and strategic decision making. Academy of Management Journal, 31(3)
後知恵バイアスとどう向き合うか
ここまで見てきたように、後知恵バイアスは判断の巧拙を単純に示すものではありません。結果を知った後で評価や説明が行われる限り、誰にとっても生じ得る認知の傾向です。重要なのは、後知恵バイアスを「避けるべき失敗」として扱うことではなく、その前提をどう受け止めるかという点にあります。
まず押さえておきたいのは、結果と判断を切り離して考えることの難しさです。判断は常に、不完全な情報と時間的な制約の中で行われます。しかし振り返りの場面では、その不完全さよりも結果の明確さが前面に出てきます。そのため、「結果が良かったかどうか」が、「判断が良かったかどうか」の代替指標として使われやすくなります。この置き換えが自然に起きてしまう点に、後知恵バイアスの扱いにくさがあります。
後知恵バイアスと向き合う上で一つの手がかりになるのは、評価の問いを少しずらすことです。「なぜこの結果になったのか」だけで振り返るのではなく、「判断時点で何が分かっていて、何が分かっていなかったのか」を確認する。こうした問いは、過去を正当化するためのものではなく、当時の判断がどのような前提の上に成り立っていたのかを言語化するためのものです。
また、振り返りの場面では、説明がきれいに整い過ぎていないかにも注意が必要です。結果を知った後に組み立てられた説明は、一貫性があり理解しやすいものになりがちです。しかし、その分、判断時点で存在していた迷いや不確実性が削ぎ落とされます。「分かっていた」「予測できた」という感覚が強まるほど、次の判断に必要な材料は、むしろ減っている可能性があります。
企業の中では、判断の結果が共有され、評価や説明が求められる場面が繰り返し訪れます。そのたびに、結果を軸にした整理だけが積み重なると、「学び」は増えているようで、実際には判断の幅が狭まっていくことがあります。後知恵バイアスと向き合うとは、過去の判断を正解か不正解かで分類することではなく、判断が行われた状況をできるだけそのままの形で捉え直そうとする姿勢を保つことだと言えます。
まとめ
後知恵バイアスは、結果を知った後で過去を理解し直すときに生じる、ごく自然な認知の傾向です。結果を前提にすれば、出来事は必然だったように見え、「分かっていた」「予測できていた」という感覚が生まれやすくなります。その感覚は、判断の評価を結果に引き寄せ、振り返りを整った説明へと変えていきます。
しかし、判断が行われた時点には、常に不確実性があります。どの情報があり、どの情報がなく、どの前提を置いて選択が行われたのか。結果を知った後の評価は、それらを見えにくくします。評価が結果中心になるほど、「学んだ」という感覚は得られても、次の判断を支える材料は十分に残らないことがあります。
司法判断や企業の戦略判断を扱った研究が示しているのは、後知恵バイアスが一部の人の失敗ではなく、結果を知った状態で評価する構造の中で生じるという点です。だからこそ、後知恵バイアスは消すべきものというより、前提として扱うべきものだと言えます。
振り返りの場面で、「なぜそうなったか」だけでなく、「当時、何が分かっていて、何が分かっていなかったのか」を丁寧に確かめる。説明が整い過ぎていないかを疑い、当時の不確実性をできるだけ取り戻す。その姿勢を持つだけでも、判断や評価の見え方は変わります。後知恵バイアスを理解することは、過去を裁くためではなく、次の判断に残すべきものを見失わないための準備になります。