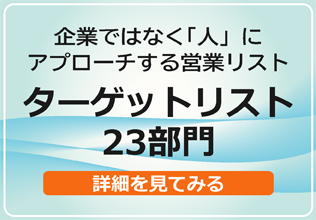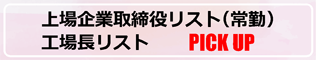2025-12-18
合理的な経営判断はなぜ失敗するのか? 論理の影に潜む「非合理」の正体
BtoB 営業・マーケティング コラム
多くの企業は、合理的な経営判断を目指しています。数字に基づき、データを分析し、論理的に検討する姿勢は、経営において欠かせないものです。ただし、十分に検討したはずの判断が、後から振り返ると別の結論もあり得たように見える場面は少なくありません。問題は合理性そのものにあるのではなく、「人は合理的に判断できる」という前提を、知らず知らずのうちに置いてしまう点にあります。本記事では、戦略意思決定を認知の観点から捉え直し、合理性をどう位置付けて考えるべきか、その前提を整理していきます。
合理的経営という前提は、どこから来たのか
経営判断において「合理的であること」が重視されるようになった背景には、長い時間をかけて形成されてきた考え方があります。数字に基づき、データを分析し、論理的に検討する姿勢は、いまや多くの企業にとって自然な前提になっています。ただし、この前提は最初から経営の世界にあったわけではなく、経済学や組織論の中で「判断とは何か」を説明しようとする枠組みが整う中で、少しずつ強化されてきました。
その起点として押さえておきたいのが、古典的な経済学で置かれてきた人間像です。古典的な経済学では、人間はすべての選択肢を把握し、完全な計算に基づいて最大の利益を選ぶ存在として想定されてきました。いわゆる「経済人」と呼ばれる想定です。この見立ては現実の人間から見れば強い単純化を含みますが、判断を理論として扱うための前提としては非常に強力でした。判断が合理的に行われると仮定すれば、選択や行動を説明しやすくなり、比較や最適化の議論も成立します。
この「合理的に判断する」という理想像は、経済学の中だけにとどまらず、経営や組織の議論にも影響を与えてきました。経営判断を属人的な勘や経験だけで語るのではなく、目標を設定し、選択肢を比較し、説明可能な根拠をもって決めるべきだという考え方は、企業活動の規模が大きくなるほど必要性を増していきます。組織が大きくなれば、個人の納得だけではなく、周囲への説明や共有が欠かせません。その意味で、合理性は「理想」でもあり「運用上の要請」でもあったと言えます。
一方で、この前提がそのまま現実に当てはまるわけではないことも、早い段階から指摘されてきました。例えば、経営学者の Simon は著書『Administrative Behavior』※1 の中で、意思決定を理論的に捉え直しつつ、人間の判断には限界があることを前提に置きました。情報をすべて集め切ることはできず、将来を完全に予測できるわけでもなく、計算能力にも限界がある。そうした制約の中で人は判断するという見方です。ここで重要なのは、合理性を否定したのではなく、合理性を「無条件の前提」ではなく「制約のある条件」として捉え直した点にあります。
この捉え直しによって、経営判断は二つの意味で整理されるようになります。第一に、合理性は依然として重要な目標であるものの、現実の判断は常に制約とともに行われること。第二に、その制約のもとで人がどのように判断するのかを、経験談ではなく分析の対象として扱えることです。完全合理を前提とした最適化の議論から一歩引きつつも、意思決定を「説明できるもの」として扱おうとする姿勢は、この流れの中でむしろ強まっていきました。
合理モデルが経営の現場で広く受け入れられた理由も、ここにあります。判断の根拠を説明しやすく、組織内で共有しやすいからです。数字や指標を用いれば、個人の感覚に依存せずに議論できるように見えますし、後から検証することも可能になります。合理性は、単に美しい理想ではなく、組織が意思決定を回していくための共通言語として機能してきました。
ただし、合理性を共通言語として扱うとき、別の前提が暗黙に置かれがちです。それは、判断に必要な情報が把握され、評価基準が共有され、意思決定者がそれらを一貫して処理できるという前提です。この前提があるからこそ、合理的な比較や最適化が成り立ちます。しかし現実の経営判断では、情報は常に不完全で、評価基準も固定されているとは限りません。さらに、同じ情報を前にしても、人によって重視する点や解釈は異なります。合理性が重要であるほど、こうした前提の揺らぎは見落とされやすくなります。
【出典】
※1 Simon, H. A. (1957). Administrative Behavior. Macmillan.

合理的に決めているはずでも、判断は揺れる
合理性を前提に判断しているにもかかわらず、結論が一つに定まらない。こうした状況は、経営の現場では珍しいものではありません。同じ市場データを見ていても、ある人は成長機会を見出し、別の人はリスクの大きさを指摘する。数値や資料に大きな差がないにもかかわらず、判断が分かれる場面は日常的に起こります。
この現象は、情報が不足しているから起きるわけではありません。むしろ、十分な情報を集め、論点を整理し、合理的に検討した結果として生じることが多い点に特徴があります。合理的に考えたはずなのに、なぜ判断は揺れるのでしょうか。
一つの手がかりは、「判断は情報そのものではなく、情報の解釈によって形づくられる」という点にあります。数字や事実は客観的に存在していても、それをどう読むか、どこを重要と見るかは判断者に委ねられています。売上の伸び率を成長と見るか、鈍化の兆しと見るかは、置かれている文脈や関心によって変わります。合理性は、こうした解釈のプロセスを完全には排除できません。
この点を明確に示したのが、行動経済学の研究です。心理学者の Kahneman は著書『Thinking, Fast and Slow』※2 の中で、人の判断が常に意識的で論理的に行われているわけではないことを示しました。人は状況に応じて直感的な思考と熟慮的な思考を使い分けており、後者を用いているつもりでも、前者の影響を受けることがあります。重要なのは、これは判断力の欠如ではなく、人間の認知の性質だという点です。
経営判断においても事情は同じです。どれだけ論理的な手順を踏んだとしても、判断者は「どの論点を検討対象にするか」「どの基準を優先するか」を自ら選び取っています。この選択は、明文化されにくい前提や過去の経験、組織内で共有されてきた価値観に影響されます。その結果、合理的に見える判断であっても、別の前提を置けば異なる結論が導かれる余地が残ります。
また、判断は常に一回限りの計算ではなく、時間の流れの中で行われます。情報が段階的に集まり、状況が変化する中で、判断の重心も少しずつ動いていきます。ある時点では妥当だった判断が、後から見ると違って見えるのは珍しいことではありません。この変化を単に「当時は見誤った」と片付けてしまうと、合理性がどこで揺らいだのかを見失ってしまいます。
合理的に決めているはずでも判断が揺れるのは、合理性が無意味だからではありません。判断が人の認知を通して行われる以上、揺らぎは避けられないものとして組み込まれています。合理性は、結論を自動的に一つに決めてくれる装置ではなく、経営判断をどう捉えるかを整理するための枠組みだと考える必要があります。
合理的に決めているはずでも判断が揺れるのは、合理性が無意味だからではありません。判断が人の認知を通して行われる以上、揺らぎは避けられないものとして組み込まれています。合理性は判断の手順を整える力にはなりますが、判断に持ち込まれる前提や重み付けまで自動的にそろえるものではありません。にもかかわらず、結論が整って見えると、前提の違いが消えてしまい、「合理的に決めた」という言葉だけが残ります。ここに、合理性を重視するほど見落としやすい落とし穴があります。
【出典】
※2 Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.
戦略判断は「情報処理」であるという視点
戦略判断を合理的に捉えようとするとき、判断はしばしば「計算」や「選択」の問題として語られます。しかし実際には、戦略判断は数式を解く行為というよりも、情報をどう受け取り、どう整理し、どう意味付けるかという一連の情報処理の過程として行われています。この視点に立つと、合理性の捉え方は少し違ったものになります。
経営の現場では、判断に必要な情報が最初から整った形で与えられることはほとんどありません。市場データ、顧客の反応、社内の制約条件など、性質の異なる情報が断片的に集まり、それらを組み合わせながら状況を理解していきます。この段階で重要なのは、どの情報に注意を向け、どの情報を背景に退けるかという取捨選択です。すべての情報を同時に、同じ重みで扱うことは現実的ではありません。
この点について、戦略判断を認知の観点から捉えた研究は示唆に富んでいます。経営学者の Schwenk は論文「The Cognitive Perspective on Strategic Decision Making」※3 の中で、戦略判断を情報処理のプロセスとして捉え、意思決定者の認知がどのように影響するかを整理しました。ここで押さえておきたいのは、戦略が「合理的に選ぶ技術」以前に、「現実をどう見立てるか」という認知の枠組みの上に成り立っているという点です。合理モデルは結論の整合性を高めますが、見立てそのものを自動的に正すわけではありません。
情報処理としての戦略判断を考えると、判断は大きく二つの段階に分けて捉えられます。第一に、外部環境や内部状況をどう認識するか。第二に、その認識に基づいて、どの行動が望ましいかを判断するかです。合理性が問題になるのは主に後者に見えますが、前者の段階でどのような認識が形成されているかによって、選択肢の幅や評価基準そのものが変わってきます。つまり、結論の合理性は、すでに認識の段階で方向付けられているということです。
この見方に立つと、同じデータを用いても異なる戦略が導かれる理由が見えてきます。どの情報を中心に据えるか、どの時間軸で捉えるか、何を変化として見るかによって、状況の意味は変わります。外部環境の変化を機会として読むか、脅威として読むかも、過去の経験や組織内で共有されてきた見方に左右されます。ここで起きているのは論理の誤りというより、情報処理の前提の違いです。前提が違えば、合理的に見える結論が複数成立します。
このように考えると、戦略判断における合理性は、与えられた選択肢の中から最適解を選ぶ能力だけを指すものではありません。むしろ、どの情報を判断材料とし、どのような枠組みで状況を理解するかという段階を含めて考える必要があります。合理的な結論に見える判断であっても、その背後にある情報処理の前提が異なれば、別の合理的結論が成立する余地は残ります。
戦略判断が情報処理である以上、合理性は計算の正確さだけでは完結しません。どの情報を拾い、何を背景に退け、どう意味付けるかが判断を方向付けます。それでも私たちは、結論が説明できる形になった瞬間に、あたかも判断全体が合理的だったかのように見なしてしまいます。合理性が必要であることと、合理性だけで意思決定の全体が説明できることは同じではありません。
【出典】
※3 Schwenk, C. R. (1988). The Cognitive Perspective on Strategic Decision Making. Journal of Management Studies.
合理モデルが見落としがちなもの
合理モデルは、経営判断を整理し、説明可能な形に整えるうえで大きな役割を果たしてきました。目標を定め、選択肢を洗い出し、評価基準に沿って比較する。この枠組みは、議論を前に進めるための共通言語として機能します。一方で、合理モデルが前提としている条件は、現実の判断環境では必ずしも満たされていません。ここに、見落とされがちな論点があります。
第一に、合理モデルは「評価基準が安定している」ことを暗黙に想定します。売上、利益、成長率など、指標は一見すると明確ですが、どの指標を重視するかは状況によって変わります。短期の収益を優先するのか、将来の選択肢を残すことを重視するのか。合理的に比較しているように見える場面でも、評価基準そのものは固定されていないことが少なくありません。
第二に、合理モデルは「問題の切り分け」が可能であることを前提にします。課題を分解し、要素ごとに検討すれば、全体として妥当な結論に近づけるという考え方です。しかし実際の経営判断では、要素同士が相互に影響し合い、切り分け自体が難しい場合があります。ある施策が短期的には合理的に見えても、組織の理解や市場の受け止め方によって、結果が変わることは珍しくありません。
第三に、合理モデルは「判断者が一貫している」ことを想定します。判断の前後で前提や関心が変わらなければ、結論も安定します。しかし、判断は時間の経過とともに行われ、情報の更新や環境の変化を受けます。判断者自身の関心や立場が変わることもあります。この変化は必ずしも非合理ではありませんが、合理モデルの中では扱いにくい要素です。
こうした点が見落とされやすい理由の一つは、『合理的に決めているはずでも、判断は揺れる』で触れた通り、判断に持ち込まれる前提や重み付けが必ずしもそろわないにもかかわらず、合理モデルがそれらを「そろっていたかのように」見せられてしまう点にあります。合理モデルは、議論や資料の形としては整合性を作るのが得意です。目標、選択肢、評価基準を並べ、比較の筋道を描けば、結論は一つのストーリーとして成立します。
しかし、そのストーリーが成立する過程で、判断の前提は暗黙のうちに整理され、固定されやすくなります。例えば、どの情報を重要と見なしたのか、どのリスクを許容したのか、どの時間軸を採用したのかといった点は、本来は判断の根幹に関わります。それでも合理モデルの形式に落とし込むと、それらは「前提」として静かに埋め込まれ、最終的には結論を支える部品として扱われます。ここで起きているのは、合理性の不足ではなく、合理性の枠組みが持つ表現上の偏りです。
さらに厄介なのは、結論がきれいに説明できるほど、その説明が「当時も同じ形で見えていた」と錯覚しやすくなることです。判断の場には不確実さがあり、選択肢も評価軸も揺れていたはずなのに、資料として整った瞬間に、判断は最初から整理されていたものとして理解されやすくなります。合理モデルは、説明責任を果たすうえで有効である一方、意思決定が本来抱えていた不確実さや前提の可変性を、見えにくくする作用も持っています。
合理モデルが見落としがちなのは、合理性の外側にあるものではなく、合理性が成立するために置かれている前提です。どの情報が重要と見なされ、どの評価軸が選ばれ、どの不確実性が許容されたのか。これらは数式や表には現れにくいものですが、判断の方向を大きく左右します。合理モデルを用いること自体が問題なのではなく、その前提が自明のものとして扱われるときに、判断の実態とのズレが生じやすくなります。
合理的経営は幻想なのか
ここまでの議論を踏まえると、「合理的経営」という言葉に、どこか引っかかりを覚えるのは自然なことです。合理性を重視し、データや論理を尽くして検討しているにもかかわらず、判断の場では迷いが生じ、後から振り返ると別の選択肢も十分に考えられたように見える。こうした感覚は、特定の例外ではなく、多くの組織で共有されているものです。
『合理的に決めているはずでも、判断は揺れる』で整理した通り、合理性は判断を支える重要な枠組みでありながら、結論を自動的に一つに収束させる装置ではありません。むしろ、合理性を重視するほど、結論が整って見える一方で、判断の前提がどこで置かれたのかが見えにくくなる場面があります。ここに、「合理的に経営している」という感覚が現実から離れていく入り口が生まれます。
この点をよりはっきりさせるのが、『戦略判断は「情報処理」であるという視点』で扱った話です。戦略は、与えられた選択肢の中から最適解を選ぶ以前に、状況をどう理解し、どう意味付けるかという段階で方向付けられています。見立てが変われば、重視される情報も、比較の軸も、選択肢の並び方も変わります。結論だけが合理的に整って見えるとき、見立ての違いは表に出にくくなります。
さらに『合理モデルが見落としがちなもの』で確認した通り、合理モデルには「結論をきれいに説明できてしまう」という特性があります。目標、選択肢、評価基準を並べれば、判断は一つの筋道として提示できます。説明が整うほど、当時の判断環境にあった不確実さや、前提の可変性は背景に退きやすくなります。合理モデルは説明責任を果たすうえで有効である一方、判断の実態を単純化し、過度に整ったものとして理解させてしまう側面も持っています。
この意味で、「合理的経営」という表現は、そのまま現実を言い当てているとは言い切れません。経営判断は合理性だけで構成されているわけではなく、認知、解釈、前提の選択といった要素と切り離せないからです。それにもかかわらず、経営を「合理的に設計されたもの」として語るとき、判断が本来抱えていた揺らぎや不確実さが見落とされやすくなります。合理性が高いほど現実に近づくとは限らず、合理性が高いほど現実が整って見えてしまう場合がある。これが「幻想」という言葉が指し示す核心です。
ただし、ここで言いたいのは合理性が不要だということではありません。むしろ逆です。合理性が重要であるからこそ、その適用範囲と限界を意識する必要があります。合理的に説明できていることと、判断の実態を十分に理解できていることは同じではありません。合理モデルを使うこと自体が問題なのではなく、合理モデルが作り出す整った見え方に引きずられたときに、現実との距離が生まれます。
「合理的経営は幻想なのか」という問いは、合理性を捨てるかどうかを問うものではありません。合理性をどの位置に置き、何を期待し過ぎてはいけないのかを見定めるための問いです。合理性を前提にし過ぎないこと。それが、経営判断に向き合う上での出発点になります。
まとめ
本稿では、「合理的経営は幻想なのか」という問いを手がかりに、経営判断における合理性の位置付けを整理してきました。ここで確認してきたのは、合理性そのものが誤っているという話ではありません。データや論理に基づいて考えることは、経営にとって不可欠ですし、その価値が失われるわけでもありません。
一方で、合理性を前提にすれば判断は自動的に一つに定まり、現実を正確に捉えられるという期待には、注意が必要です。判断は人の認知を通して行われ、情報の意味付けや前提の置き方によって方向付けられます。合理モデルは結論を整え、説明可能な形にする力を持ちますが、その整った姿が、判断の実態をそのまま映しているとは限りません。
合理的に説明できていることと、判断の前提や不確実さまで含めて理解できていることは同じではありません。合理性が高いほど、判断が整って見え、その背後にあった揺らぎや解釈の違いが意識されにくくなることもあります。この意味で、「合理的経営」という言葉は、現実を過度に整ったものとして捉えてしまう危うさを含んでいます。
だからといって、合理性を捨てる必要はありません。重要なのは、合理性が何をできて、何をできないのかを見極めた上で用いることです。合理モデルを使うこと自体が問題なのではなく、そのモデルが作り出す見え方に無自覚なまま判断を委ねてしまうことが問題になります。
合理性を信じることと、合理性に委ね過ぎないことは両立します。その間に立つ視点こそが、経営判断の現実を捉えやすくします。