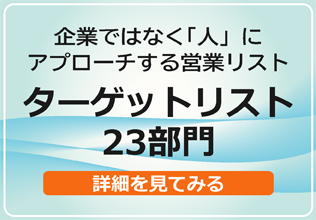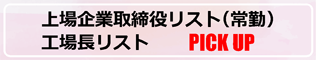2025-05-22
AIを前提に考えるマーケティング戦略 ― 人が本当に担うべき役割とは
BtoB 営業・マーケティング コラム
生成AIの実用化が加速し、マーケティングの現場にも急速な変化が訪れています。コピーの草案づくり、ユーザー行動の予測、チャットボットによる対応など、かつて人の手を必要としていた業務の一部は、今やAIによって代替可能になりました。
こうした流れの中で、あらためて突きつけられているのが、「私たち人間はどこで価値を発揮するのか」という問いです。AIによって多くの作業が効率化されていく一方で、マーケターに求められる役割はむしろ広がっているとも言えます。
どの判断を任せ、どこに関与し、どんな視点を持つべきか。これまでの延長線では語りきれない局面に、私たちは立たされています。
本稿では、AIを前提とする時代におけるマーケティング戦略の変化を捉え、人間ならではの役割とは何かを掘り下げていきます。
目次
AIが変える“作業”の風景
マーケティング領域でAIが実用化されはじめた当初は、分析や自動化といった限定的な使い方にとどまっていました。しかし現在では、文章生成、画像編集、音声合成など、表現に関わる領域までその活用範囲が広がっています。特に生成AIの進化は目覚ましく、少ない指示から広告文案の素案をつくり、複数パターンを一瞬で出力することも当たり前になりつつあります。
こうした状況下では、従来「人の手によってしか行えない」とされてきた作業の多くが、すでに再定義の対象になっています。たとえば、メールのパーソナライズ文やキャンペーンごとの見出しづくりは、AIの力を借りることで短時間で高い精度の出力が可能になります。さらに、顧客の行動データをもとに提案内容を変化させるレコメンドエンジンも、AIによって進化を続けています。
特筆すべきは、こうした変化が単なる「効率化」にとどまらない点です。時間短縮や工数削減という効果に加えて、そもそもの仕事の進め方そのものが見直されるようになってきました。従来は経験や勘に頼っていた領域においても、AIが一定のアウトプットを示すようになったことで、人の関与のあり方に変化が生じているのです。
もちろん、すべての作業がAIに置き換わるわけではありません。ただし、ルール化やテンプレート化が可能な業務については、AIに委ねることの合理性が急速に高まっています。そしてその結果として、マーケター自身が担うべき役割の“重心”が、従来と比べて確実に動きつつあります。

意思決定を支える「前提」の質
AIの活用が進むほどに浮かび上がってくるのは、「どんな条件でAIに仕事を任せるか」という前提設定の重要性です。AIは与えられた指示に対して高速かつ大量に出力を行いますが、その精度や方向性は、どのような前提で運用されているかによって大きく左右されます。
たとえば、あるキャンペーンにおける成果指標を何に置くか――クリック率なのか、商談化率なのか。それによって最適化の方向性はまったく変わってきます。AIは条件に忠実であるがゆえに、判断基準や設計思想が曖昧なままだと、出力内容もそれに応じて不安定になります。
これは分析の場面に限らず、クリエイティブ領域にも同様のことが言えます。コンテンツのトーン、想定している読者の温度感、伝えたい優先順位といった要素は、あらかじめ人間の側で決めておかなければ、AIは的外れな提案を返してくることがあります。言い換えれば、AIが力を発揮するためには、前段階の「設計力」が問われるのです。
この設計力とは、単にルールを決めるという話ではありません。背景にあるビジネス環境や顧客の変化、競合の動きなどを踏まえながら、「今、何を優先すべきか」を見極める判断そのものです。ここにおいては、現場の経験や観察眼がものを言います。むしろ、AIの出力を鵜呑みにせず、意図や仮説をもって向き合えるかどうかが、その成果を左右すると言っても過言ではありません。
AIを活用した意思決定は、あくまで人間が設計した前提のうえに成り立つものです。そして、その前提の質こそが、最終的な成果の質を決める鍵になっています。
「共感」や「違和感」の精度が差を生む
マーケティングにおける表現や訴求は、論理だけでは語りきれない領域です。数字に表れない要素、言葉の選び方ひとつで伝わり方が変わる場面が日常的にあります。こうした繊細な調整において、AIと人との違いが顕著になります。
たとえば、あるキャッチコピーが文法的にも内容的にも正しく、訴求軸もマーケティング上は間違っていなかったとしても、なぜかしっくりこない、どこかずれていると感じることがあります。この「どこか」の違和感を察知できるのは、顧客の目線に立ち、実際のやりとりや反応に触れてきた人間ならではの感覚によるものです。
逆に言えば、そうした微細な“感情のノイズ”に気づけるかどうかが、成果の差を生むことも少なくありません。言い換えれば、共感の精度を高めることができるのは、文脈を理解し、相手の置かれている状況を想像できる人間の力です。
また、ターゲットが言語化できていない本音や、場面ごとの空気感など、データとして取得できない情報は依然として多くあります。これらを読み取り、表現に反映させるには、人ならではの観察眼や実感値が必要です。
AIが生成したコンテンツに対し、「なぜか冷たく感じる」「これは少し押しつけがましい」と感じたとき、その違和感を言葉にし、軌道修正できるかどうか。ここにマーケターとしての重要な判断力が求められます。
単なる表現の正しさや体裁の整いではなく、「伝わるかどうか」にまで踏み込めるか。それは、共感や違和感といった非定量的な感覚にどれだけ敏感でいられるかにかかっています。
創造性とは「結びつける力」である
創造性というと、何もないところから斬新なアイデアを生み出す力を想像しがちですが、実際の仕事の現場では、既存の情報や要素をうまく結びつける力こそが重要になります。とくにマーケティングのように多様なデータや観点が交差する領域においては、その傾向がより顕著です。
たとえば、ある業界で話題になっている課題感と、自社の知見や実績。あるいは、過去の顧客インタビューと市場の変化。こうした異なる視点や素材をつなぎ合わせて、新たな切り口を見出すことが「創造的な提案」につながっていきます。
AIも膨大な情報を横断し、関連性の高い組み合わせを提示することはできます。しかし、その中から「何を選ぶか」「どこに価値を見出すか」は、依然として人間の判断が必要です。無数の候補の中から、文脈に合い、今の市場にフィットし、かつ自社らしさを感じさせる一案を選び取る作業には、思考の深さと経験が問われます。
また、構成や順序といった“見せ方”の工夫も、人の創造性が大きく関わる部分です。同じ情報でも、どう語るか、どう並べるかによって伝わり方はまったく異なります。意味のある結びつけ方ができるかどうかが、そのまま戦略の強度に直結します。
創造性とは、突飛な発想を競うものではなく、目的に沿って要素を組み立て、価値あるかたちに仕上げる力です。AIが生成する無数の“候補”はあくまで素材であり、それを活かすも捨てるも、人間の目と判断にかかっています。
分業から“連携” ― チームの変化と個人の役割
AIがマーケティング業務に組み込まれるようになって以降、チームの仕事の進め方も少しずつ変わってきています。かつては、企画、制作、分析といった工程ごとに明確な担当を割り振る“分業型”のスタイルが一般的でした。しかし今では、AIを間に挟んだワークフローにおいて、各メンバーが単に自分の役割を果たすだけでは不十分になりつつあります。
というのも、AIの出力は万能ではなく、常に人の判断と調整を必要とするからです。あるメンバーが生成したコピー案を、別のメンバーが読んで微調整を加えたり、AIによる顧客セグメントの提案に対して現場感をもとに再評価を行ったりする。こうした“行き来”が自然と生まれることで、成果物の精度が高まっていきます。
このような働き方では、メンバー間の情報共有や相互理解が欠かせません。役割を区切るのではなく、それぞれの視点を持ち寄り、AIの出力をもとに柔軟に意思決定していく――そうした“連携型”の仕事の進め方が、次第に主流になりつつあります。
また、個人の役割にも変化が見られます。かつては「手を動かして何かを作る」ことがその人の貢献を示していましたが、現在では「状況を読み、正しく判断し、必要な修正を加える」ことの重要性が増しています。AIを活用することで作業量そのものは減っても、その分だけ“見る力”や“選ぶ力”が求められるようになっているのです。
単純なアウトプットの多寡ではなく、出力の質を高める働きができるかどうか。それが、これからのチームにおける個人の価値を決める要素になっていくでしょう。
戦略の質を決める「問い」の立て方
AIが優れた出力を返すようになった今、ますます重要になっているのが「どんな問いを立てるか」です。どれほど高度な演算能力を持っていたとしても、AIは自律的に問いを設定することはできません。何を目的とするのか、どこを掘り下げるのかといった前提は、常に人の側から与えられる必要があります。
マーケティングにおいても同様で、「今の市場で本当に向き合うべき課題は何か」「顧客が言語化していないニーズはどこにあるのか」「成果が出ていない要因は本当にコンテンツの問題なのか」など、問いの立て方によって導かれる解がまったく変わってきます。逆に言えば、問いが浅ければ、いくら正確に答えを導いても戦略の軸はぼやけたままです。
こうした問いを立てるには、現場の状況や過去の経験、業界特有の文脈への理解といった、AIが持ち得ない視点が欠かせません。さらに、問いの粒度や切り口にも工夫が求められます。単に「売上を伸ばしたい」ではなく、「どの層に、どう届いていないのか」「既存顧客との関係性に何が欠けているのか」といった具体的で本質に迫る問いを設計できるかどうかが、戦略の質を左右します。
問いを立てるとは、仮説を持つことでもあります。今見えている情報だけでは判断できない領域に対し、あえて踏み込む姿勢を持つこと。そして、そこから新しい検証や見直しが生まれる構造をつくることが、AI時代のマーケティング戦略における人間の重要な役割です。
優れた問いは、単に答えを導くための道具ではありません。それ自体が戦略を動かす起点となり、組織の思考を深めていく力を持っています。
まとめ
AIの導入が広がり、マーケティング業務にも本格的に活用されはじめた今、人間の役割はむしろ明確になってきたと言えるかもしれません。ルール化できる作業はAIが担い、データに基づく処理も高速化されていく一方で、その基盤の上に何を築くかは、依然として人の判断に委ねられています。
AIの出力を活かすには、前提となる設計や問いの質が問われます。そして、その設計には状況の理解や市場の文脈、顧客の感情への感度といった、数値では置き換えにくい視点が必要です。また、出力された候補の中から最も適切なものを選び、整え、伝わる形に仕上げる創造的な力も、人間ならではの強みです。
加えて、AIを活用することで個人やチームの働き方そのものも変わりつつあります。単なる分業ではなく、お互いの視点や判断を持ち寄る“連携型”のスタイルが重視されはじめており、その中で求められるのは「量よりも質」に向き合う姿勢です。
AIは、私たちの仕事を奪うものではなく、拡張するための道具です。そしてその道具をどう使うかは、私たち次第です。与えられた選択肢の中から最適解を選ぶだけでなく、自ら問いを立て、方向性をつくっていく。そうした「前に出る力」が、今後のマーケターにとってより重要になっていくのではないでしょうか。